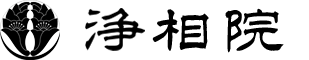つながる想い
めぐる供養
つながる想い
めぐる供養
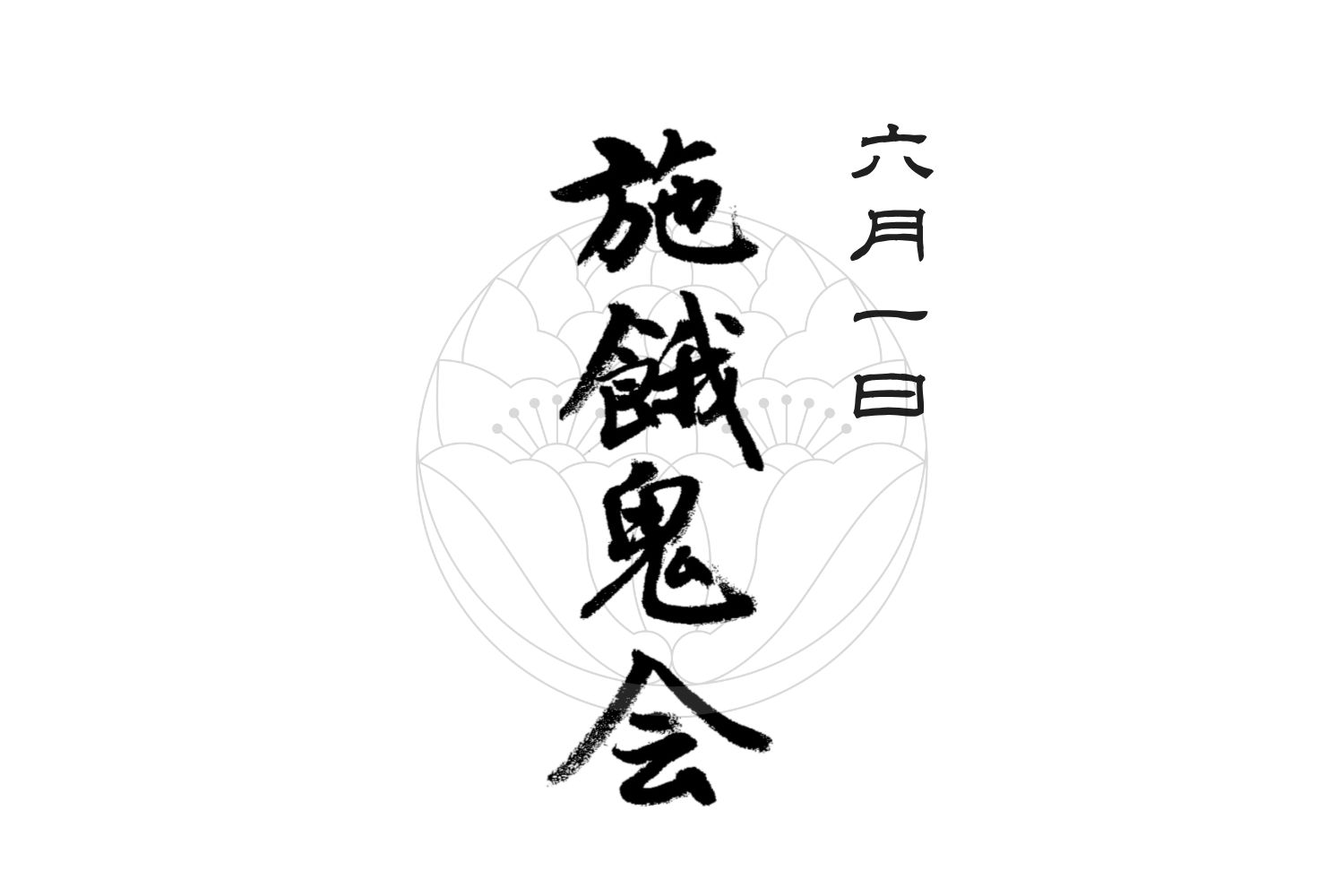
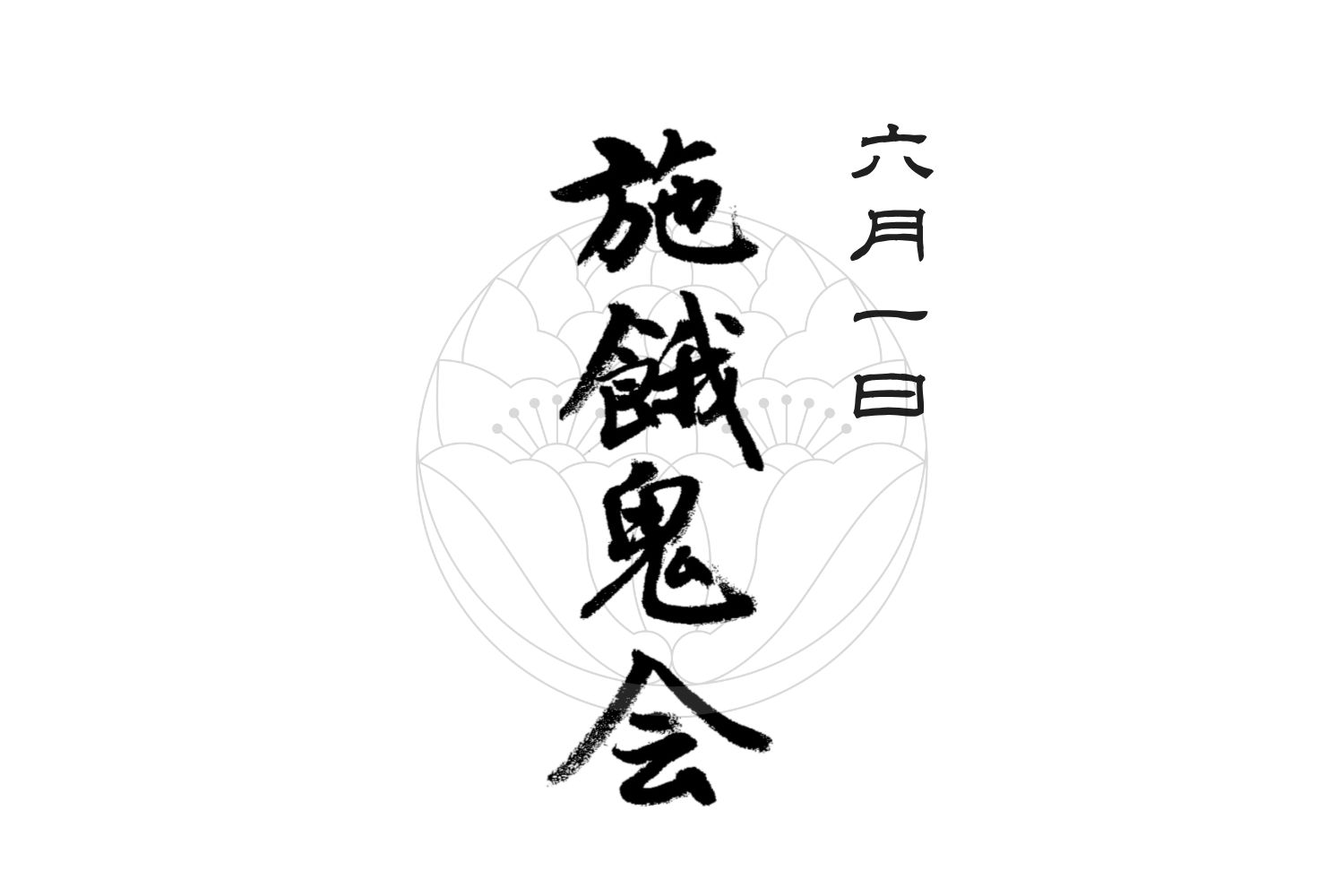
施餓鬼会(せがきえ)
施餓鬼(せがき)は、死後に「餓鬼道(がきどう)」という世界に堕ち、飢えや渇きに苦しむ霊魂に食物や飲み物を施し、供養する儀式のことです。正式には「施餓鬼会(せがきえ)」と呼ばれ、また「お施餓鬼」とも親しまれています。
施餓鬼会とは、名前の通り「餓鬼(がき)に施しをするため」の法要です。
「餓鬼」とは、生前に物を惜しんだり、嫉妬や欲にとらわれた結果、死後に食べ物や飲み物を自由に取ることができず、いつも飢えと苦しみに悩まされている存在のことです。
施餓鬼会では、そうした餓鬼へ食べ物や飲み物を施し、お念仏の力(功徳)を届けて、少しでも苦しみから救われ、極楽浄土に生まれ変わることを願います。
また、この法要を通して得られる善行の力(功徳)を、ご先祖さまや大切な亡き人に届けることも、大切な意味の一つです。
施餓鬼会は、亡くなった方の供養だけでなく、私たち自身の心の中に「分かち合い、支え合う気持ち=布施の心」を育てる機会でもあります。
施餓鬼の由来と伝承
施餓鬼(せがき)の由来は、『救抜焔口餓鬼陀羅尼経(くばつ えんく がき だらに きょう)』というお経に出てくるお話がもとになっています。
ある日、お釈迦さまの弟子のひとりである阿難尊者(あなんそんじゃ)が瞑想をしていると、焔口(えんく)という餓鬼(がき/飢えに苦しむ亡者)があらわれて、「あなたは三日後に、私たちと同じように餓鬼道に落ちることになる」と言われてしまいます。
驚いた阿難尊者がお釈迦さまに相談すると、「たくさんの餓鬼や僧侶に食べ物を施し、お経を唱えなさい」と教えられました。その教えの通りに行うと、多くの餓鬼たちが救われ、阿難尊者自身も助かって、寿命が延び、最終的には悟りを開いたと伝えられています。
このお話が、施餓鬼という供養の行事の始まりとされています。
一般的に「お盆」は、自分のご先祖さまを供養するための行事ですが、「施餓鬼」はそれだけではなく、縁のない人たちや、苦しんでいるすべての霊に対しても供養をするという点が大きな特徴です。
お盆が「身近な人たちの供養」なのに対して、施餓鬼は「誰にも供養されない霊もふくめて、すべての命を供養する」行事になります。
開催日時
| 施餓鬼会 | 令和7年6月1日(日)13:30〜(受付13:00) |
【会場】浄相院
当日の流れ
| 受付 | 13:00〜 外階段から2階へあがり、受付がございます |
| 法話 | 13:30〜 滋賀教区 正定寺 前住職 佐々木昭道 上人 |
| 法要 | 14:20〜 |
アクセス
| 所在地 | 〒332-0035 埼玉県川口市西青木1-10-34 |
|---|---|
| アクセス | 西川口駅 から徒歩12分 川口駅 から徒歩17分 西川口駅からバス(西川05) 「県税事務所バス停」 から徒歩1分 |
| 駐車場 | 駐車場完備しております。車でお越しいただけます。 |
浄相院は、西川口駅から車で約5分のところにあります。駐車場がございますので、どうぞご利用ください。公共交通機関でお越しの場合は、JRをご利用ください。JR京浜東北線「西川口駅」から徒歩12分、JR京浜東北線「川口駅」から徒歩17分でお越しいただけます。