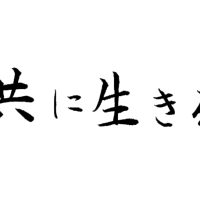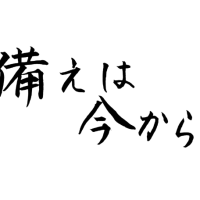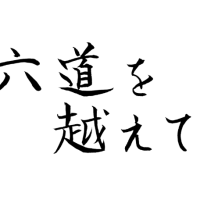生の最後の行為のように(3/4)


かつては、お盆は今よりもずっとずっと人々の暮らしに深く根づいた大切な行為だったように思われる。明治生まれの私の母もお盆を迎えるにあたり、押し入れから折りたたみの小机を出して、その上にお供えものを並べたり、提灯を飾ったり、準備に余念がなかったことを子供ごころに記憶している。一年に一度、先祖の霊を我が家に迎え、一緒の時間を共有し、再び送りだすという行事には、先祖への敬いと親しみと懐かしさが強く感じられる。そこにあるのは、死者との交歓であり、死そのものとの触れあいである。
人生における四苦の一つに、いや最後に「死」がある。これほどに重い苦はあるまい。死は苦そのものとも言える。人は生き、そして死ぬ。必ず死ぬ。一個の人間にとって、これほどに切実で痛烈で深甚なテーマがあろうか。だからこそ、死は「表現」にとって最初の、そして最大の衝動となり動機となる。その結果、文学があり、絵画があり、音楽があり、演劇等の表現があり、その最後に、いやそのそもそもの始まりに、宗教がある。
古代ローマ皇帝のマルクス・アウレリウスは『自省録』で、「すべての行為を生の最後の行為のように行う」と書いている。これは実に強い言葉である。実に激しい言葉である。実に重い言葉である。そして凡なる私にとって行うに実に困難な言葉である。
すべての行為を今日が、今が最後だと思って行え。明日があるから、いつかがあるからと思ってその行為を軽んじたり、いい加減に扱ったりしてはいけない。何事ももう二度とはないのだと思ってベストを尽くせ。おそらくアウレリウスもそう言って自分自身を鼓舞しながら生涯の日々を生きたにちがいない。
芭蕉の言葉に「平生すなわち辞世なり」がある。平素の一句一句が辞世である。常日頃、これが最後の一句だと心得て言葉を紡げ。わずか十七文字の中に辞世を詠み込め、という芭蕉の俳句道の厳しさと深さがここにある。