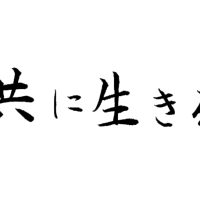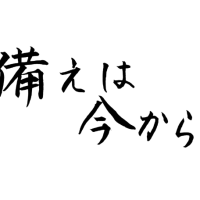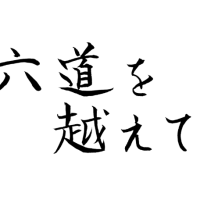何ものにも代え難い善きもの(4/4)


この連載エッセイで私は、人生における四苦「生、老、病、死」を、一つずつ順番をずらして、「老」で始めて「病」「死」とつなぎ、最後を「生」で結ぶことにする。四苦は「死」で終るのではなく、「生」で始まると同時に「生」で終るものだと思うからである。つまりは、「生」こそが人間にとって最大のテーマであり、最も深く最も重く追求されるべき課題なのだから。
たしかに「生」は苦である。そもそも「生」それ自体にさまざまな困難が内包されている。例えば、家族。金銭、就職、恋愛、結婚、競争、人間関係など、数えあげれば限りがない。そして生きているからこそ、老いもすれば、病気にもなり、死を迎えねばならない。だから「生」はすべての苦の始まりであり、あらゆる苦の代名詞でもあるのだ。
しかし、「にもかかわらず」、いやあるいは、「であるがゆえに」、生きることは感動や歓喜や至福といった多くの善きものに満ちている。生の肯定感を追求しつづけた作家の辻邦生は『モンマルトル日記』の中でこう書いている。≪時のうつり、死、病気がなかったら、この「生のよろこび」はなくなるだろうし、日々は砂を噛むような繰りかえしにすぎなくなる。生の目的というものがあるとすれば、立身するのでも金持になるのでもなく、その置かれた場所で、ただちに、この「生のよろこび」に深く同化し、生を成就させることなのだ。≫
そうなのだ、自分が今いる場所で、どれだけ深く「生のよろこび」を自覚し、味わい、同化することができるかに、生きることの真の意味があるのではないだろうか。もう一度、辻邦生を引用すれば、≪しかもこの「生のよろこび」はただ死を媒介としてのみ永遠のものとなり、あらゆる面において輝きだす≫のである。たしかに「生」は苦である。しかし、と同時に、よろこびという何ものにも代え難き善きものに満ちてもいるのだ。